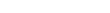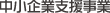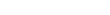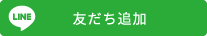賃金引き上げに向けた取組事例
-
CASE STUDY 57
賃上げ取り組み事例 -
秋田酒造株式会社
日本酒製造
2025/3/14
厳しい経営環境でも継続的な賃上げ
業務効率化、商品開発、販路開拓で苦境打破を目指す。
- 企業データ
-
- ●代表取締役社長:野本 翔
- ●本社所在地: 秋田県秋田市
- ●従業員数:11名
- ●設立:1908年
- ●資本金:1,000万円
- ●事業内容: 日本酒製造

伝統ある酒蔵に吹く厳しい逆風
全国有数の米の生産地である秋田県。「あきたこまち」など、全国で高い評価を受けるブランド米を数多く生み出す地であることは誰もが知るところだ。そんな秋田の地で100年以上日本酒製造を営んできた歴史を持つ秋田酒造株式会社。地元の米を使用して製造した日本酒は数々の品評会で賞を受けるなど、高い評価を受けている。とはいえ、同社は数多くの困難にも直面している。それでも歴史ある酒蔵を守るため、野本社長は奮闘する。
日本酒業界は、構造的不況にさらされている。日本酒の需要は、ビールやワインなど他の酒類との競争などから、50年ほど前をピークに4分の1から5分の1ほどに大きく減ってしまった。その上、近年は新型コロナウイルスの流行によって酒類の需要が減ったことも需要の減少トレンドに拍車をかけた。日本酒製造に必要な米の価格も高騰している。さらには、日本酒は最終的には消費者が購入するBtoCの商品であるため、製造費用の高騰分の全てを価格転嫁することは容易ではない。
同社がある秋田市の新屋地区には、かつて10以上の酒蔵が存在した。しかし、日本酒をとりまく厳しい環境から徐々に数を減らし、今ではこの地区で酒造りを続ける酒蔵は同社のみとなってしまった。

業務効率化により賃上げ原資を確保
同社は、経営環境が厳しくとも従業員の貢献に報いたいという思いから、従業員の賃金を引き上げてきた。しかし、賃上げするといってもその原資がなければ実現できない。
そこで、野本社長は業務の効率化に着手した。日本酒の製造に欠かせない米麹を作るためには、麹室の温度を麹菌が繁殖しやすい温度に保つことが欠かせない。麹製造に必要な温度管理を効率化するため、業務改善助成金を活用して麹室に新たにパネルヒーターを導入した。これにより、麹室の温度を麹菌の繁殖に適した温度に保つことができ、麹製造にかかる時間が大幅に短くなった。また、麹室の温度を管理するためには夜間も工場内に管理者が必要だったが、温度情報をクラウド化したことで、どこからでも麹室内の温度をモニタリングできるようにした。この結果、従業員の超過勤務を減らすことができた。さらに、瓶に酒を詰め込んだ後に行う栓付け作業や酒瓶へのラベル張り作業を自動化する機器を導入したことによって、少ない人手で作業を行うことができるようになった。「おいしい日本酒を届けるため、一つひとつの工程を誤りなく行うことは大事。でも、日本酒のクオリティを保ちつつも改善できるところはたくさんある。」と野本社長。品質の維持と業務効率の改善を両立させる工夫が、同社の酒造りのいたるところに施されている。
これらの業務効率化により、2024年度はパート従業員の賃金を中心に時給換算額で45円の引き上げを達成することができた。

(新たに導入したパネルヒーター)

(仕込み作業の様子)
苦しい状況でも継続的な賃金引き上げを目指す
同社は、業務効率化に取り組む以外の方法でも経営努力を重ねている。例えば、同社は海外に目を向け、販路開拓に取り組んでいる。海外販売の比率を高めた結果、現在では海外向けが売り上げ全体の3分の1程度となっている。これにより、国内向けの売り上げの減少を、海外向けによってカバーできている。さらに、同社の主力商品である「秋田晴」に、新たに「エース」シリーズを追加した。異なる味や香りを持つ商品を開発し、消費者の多様化する嗜好に沿った商品を売り出そうという戦略だ。野本社長は静かに、力強く語る。「伝統を守ることも大事。でも、時代の変化に応じて酒造りは変わらないといけない。」従業員の雇用と歴史ある酒蔵を守るため、社長の挑戦はまだまだ続く。

(野本翔代表取締役社長)