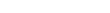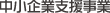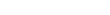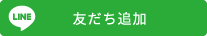賃金引き上げに向けた取組事例
-
CASE STUDY 58
賃上げ取り組み事例 -
株式会社 美安簡
生鮮食料品小売業
2025/3/31
賃金は全体で5%アップ。業務改善助成金で導入したPOSレジシステムで数量・金銭管理。人ゆえの目利き・調理でファン獲得。
【地場野菜、手作り惣菜で地域の台所に。創意工夫によって、食を通じた人との繋がりを広げていく】
- 企業データ
-
- ●代表取締役社長:石原 久二康
- ●本社所在地: 静岡県浜松市
- ●従業員数:24名
- ●設立:2018年
- ●資本金:300万円
- ●事業内容: 生鮮食料品小売業

競争は厳しいが、同じ土俵では勝負しない
野菜が食卓にまったく上らないという日はない。ハンバーグの横に添えられたニンジンのグラッセ、焼き魚の横に置かれた小鉢にホウレン草のおひたし・・・等々。野菜は、毎日、勝負できる商品だ。
青果販売には、これまで培ってきたノウハウがある。大手のスーパーでは売っていない地元産の野菜を、毎日、市場に行って仕入れる。その日に仕入れた一番良い商品を提供できるよう、鮮度を大切にし、季節感が出るような売場の工夫をしている。
また、手作り惣菜に力を入れている。特に煮物は、火加減等が難しい。マニュアル化できないものは、大手のスーパーでは作れない。だから、作る。“高付加価値商品”というと即物的な言い方になるけれど、おいしい食べ物はちょっとくらい高くても食べたくなるものだ。大ロットは必要ない。材料を使い切ったら、販売終了。材料費等は高騰しているが、商品にファンがついてくれれば、値上げをしてもきちんと売れる。
競争は厳しいが、大手のスーパーと同じ土俵では勝負しない。それが、生鮮市場Bi・an・canの強みだ。

できるところは効率化して、必要な部門へ人材を
2024年9月に業務改善助成金の申請を行い、労働者の賃金を引上げるとともに、POSレジシステムを導入した。POSレジシステムの導入前は、商品発注をする際、用紙に商品や数量を手書きしてFAXする、あるいは発注端末で商品を探して数量を入力しており、時間がかかっていた。また、発注業務とレジ業務を兼務していたため、繁忙期には、商品の誤発注、未発注、数量間違いなどが発生し、過剰在庫や廃棄ロスの原因になっていた。さらに、キャッシュレス精算のお客様が増えてきており、現金精算しているお客様の後ろで待たされているといったことも頻繁にあった。
POSレジシステムの自動発注機能によって、発注業務に人員を割く必要がなくなり、店の売上げに直結する加工部門に増員できるようになった。また、発注ミスがなくなり、チャンスロス、値引きロス、廃棄ロスが半減した。
お客様の流れもよくなった。
バックオフィス業務は、クラウド活用等のDX化を進め、1人しか配置していない。それ以外は、現場で仕事をしてもらっている。事業を支えるのは現場だ。その現場に多くの人が投入できるのは、大きい。他にも、設備投資や差別化できない商品等の仕入れは、全日食チェーン商業協同組合のスケールメリットを活かし、コスト削減等を図っている。

(新しく導入したPOSレジ)
ご縁とファンと共に
賃金は、従業員全員を対象として、全体で約5%引き上げた。賃上げを通じて得られた効果としては、従業員の意欲の向上と雇用の安定化だ。人手不足は感じていない。採用は、60~70歳の方を喜んでという方針。求人は出したことはない。張り紙をしたら応募してくれる。近隣の店で定年になった人、近くに住む経験者の人、中には生鮮市場Bi・an・canのファンの人といった方々に、今、働いてもらっている。
もっと、トンガリたい
これから会社をどうしていきたいか?との問いに「もっと、トンガリたい」。
船を持ちたい。畑もやりたい。飲食店を出すのもいいかもしれない。
自社の船で魚を獲り、自社の畑で野菜を栽培する。その時々の新鮮な素材を使って調理する。時間が経つと、味が落ちてしまうものなどは、飲食店で提供する。ある程度、保存が利くものは、惣菜として生鮮市場Bi・an・canで販売する。
店舗を増やして横に展開するよりも、材料の調達からエンドユーザーへの提供まで、縦の軸を繋いでいく方が面白いと感じている。アイディアはある。
生鮮市場Bi・an・canは、他にはない創意工夫によって、食を通じた人との繋がりを広げていく。